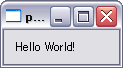Disqus のスケール - Django で月間80億PVを処理する
私が把握してる限り Django で一番大きなサービス Disqus のスケール (執筆時点ではサービスダウンしてる)。元ネタは Scaling Django to 8 Billion Page Views です。 月間80億PV 、 45k req/s のほぼすべてのトラフィックを Django で処理しているとのこと。抄訳になるかな。 WAF は 高速開発とパフォーマンス 、 新しい人が入ってすぐに開発に参加できることとカスタマイズ 等のトレードオフがあります。この記事ではそのトレードオフである高速開発とパフォーマンスをどう両立させるか、Disqus のノウハウが紹介されています。 >>> なぜ WAF (Web Application Framework) は遅いのか 最初に思い浮かぶのは、アプリケーションに必要ではないボイラープレート ( django.contrib とか?) や不要なコードがあるため。そもそも Django の思想が Python 同様 " バッテリー同梱 (batteries included) " のため、Django は他の Python 製 WAF よりボイラープレートが多いです。Disqus 曰く "実は 言語や WAF は遅さにあまり関係ない " それより " ネットワーク内の他のサービスとの通信 " のオーバーヘッドが原因とのこと。これは一般的によく言われてることですし、大規模になればなるほどそう。Disqus の場合は PostgreSQL, redis, Cassandra , Memcached 等のサービスが使われているそうです。DB へのスロークエリーやネットワークのレイテンシーは Django のようなボイラープレートによるオーバーヘッドを軽く上回ります。この待ち時間を回避する一番メジャーな方法はキャッシュの使用です。Django では キャッシュフレームワーク を使用します。Django でキャッシュを使うのは簡単ですし、バックエンドに Memcached を使うと充分高速化できます。 はい。ここまでは一般的な話です。こっから。 >>> 45k req/seq を処理する キャッシュしたところで...